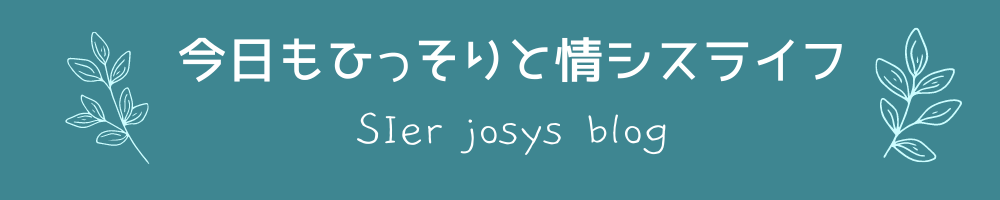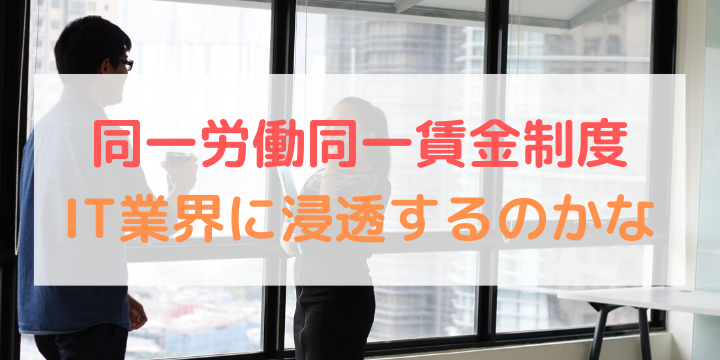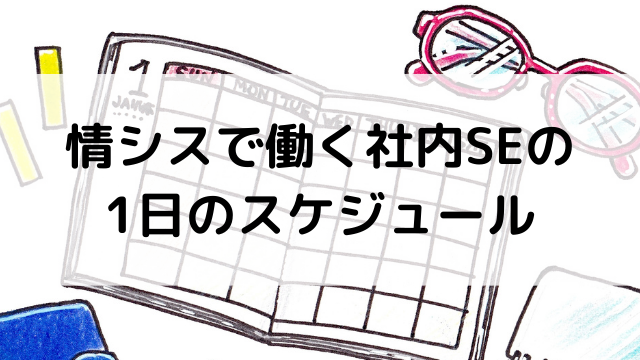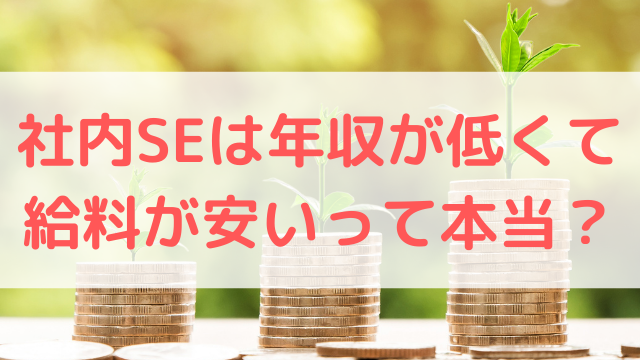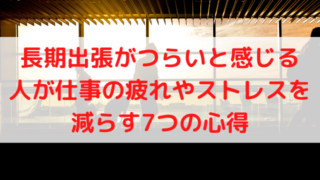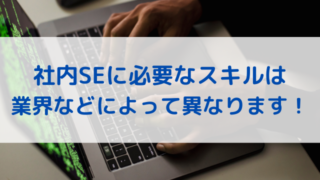先日、とある協力会社さんに「同一労働同一賃金制度が始まるね」と言われた。
一瞬「こりゃ皮肉だな」と思ったが、こんな皮肉はサラッと流して笑い話に変えられないとITの世界でチームリーダなんて務まらない。でも色々思う節はある。
IT業界では、同じ現場に契約形態の異なる色んな会社の人が似たような仕事をしていることって少なくない。ユーザ企業のSEや一次請けのエンジニアは高い報酬をもらう一方、協力会社として参画する二次受け三次受けのエンジニアは徐々に報酬が安くなってしまう。
そんな業界構造に対する不満はネット上でもよく目にするけど、そんな不満たらたらな人たちに常駐してもらう側としても 、さっさと是正されればいいのにと思っている。
だって彼らにはちゃんと月100万前後の単価を払っているのだから。この金額は元請け企業の社員の原価よりよほど高い。中抜きするやつが悪いんだよ。
そりゃ人材の調整弁となる立場の人たちはある程度必要なのかもしれないけど、協力会社ありきで開発が回っている、つまり協力会社社員を自社の社員として採用しちゃってもさほどコストが変わらないプロジェクトなんて山のようにあるのではないだろうか。
だったら雇えばいいじゃん。その方がマージンも減って、プロジェクトとしては同じコストでも労働者の手元に落ちるお金の割合は増えるはずなのだから。
大体、中抜きされているマージンなんて最終的には仕事しないバブル入社のおじさん達やスタッフ社員たちの賃金になるだけであって、開発の現場で四苦八苦している社員の元に流れるお金なんてたかが知れている。
しかし中抜きされる側の不満は開発の現場の社員へしか向けられない。 果たして、同一労働同一賃金制度の波がこんな構造のIT業界に押し寄せたら一体どうなるんだろうか、そもそも押し寄せるんだろうか。
ということを、少し考えてみました。
同一労働同一賃金の、”同一”とは誰と誰が対象?
まず同一労働同一賃金の定義をはっきりさせたい。国が作った制度なんだからお役所の情報が最も信憑性高いはず。
ということで厚生労働省の情報を確認してみると、
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
出展:厚生労働省同一労働同一賃金特集
と定義されている。あくまで同一の「企業」、「団体」に属する人が対象になる模様。 つまり、正社員の立場で客先に派遣されるSEには適用されないようだ。
となると同一労働同一賃金の制度は、IT業界の構造改善には全く役立たないということになります。
制度の目的はわかるのだけど、IT業界、特にSIerの世界では様々な会社に所属する人が同じプロジェクトで似たような作業をすることなんて頻繁にあるので、制度の狭間に埋もれてしまっているような気がしないでもない。
私は正社員のSEの方とは良く働くけど、非正規雇用の人と一緒に働く経験が乏しいので(せいぜいフリーランスの人くらいだろうか、でも彼らは不安定な待遇の対価に下手な会社員よりも高い報酬を貰っている。)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差というものがいまいちピンとこない。
でもこの制度のフォーカスが非正規雇用労働者に当てられるということは、世の中的にIT業界のこの構造よりも非正規雇用の制度が問題視されているからなのだろう。
国の制度に頼らず、自分で道を切り開くしかない
同一労働同一賃金でIT業界の多重請負構造は変わらない。それが少し調べてわかった結論です。
この業界に長くていて思うのは、いわゆる下請けと呼ばれる会社に所属する人たちの中にも非常に優秀なSEはたくさんいる。 だけど彼らに共通するのは、自分の希望がなかったり、自分の意思で行動を起こす力が弱い人が多い。
ちょっと行動を起こせば似たような仕事をして年収の100万200万簡単にあげられるはずなのにな、とよく思う。
やはり正当にSEが技術力を評価されるためには、ピラミッド構造の下の方にいてはいけないと思う。システムを運用しているお客様と直接会話ができない立場ではどうあがいてもやりがいのある仕事ができなければ給料も上がらない。
日本のIT業界の構造は多くの人がおかしいと思っていると思うのだけど、変えられないことにおかしいと言い続けるよりもこの構造の中でどう立ち回れば自分に最もリターンが返ってくるか考えて行動したほうがよほど効率が良いように思える。
同一賃金同一労働の制度をIT業界に当てはめた結果、そんな風に思うのでした。