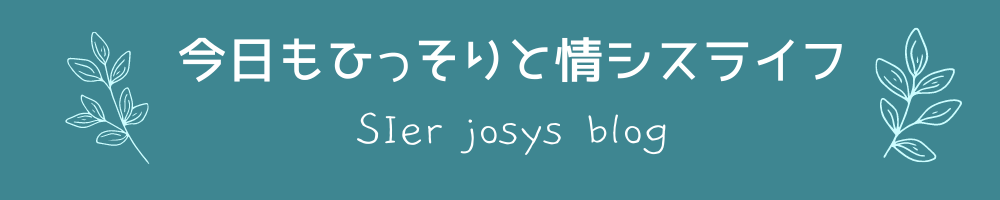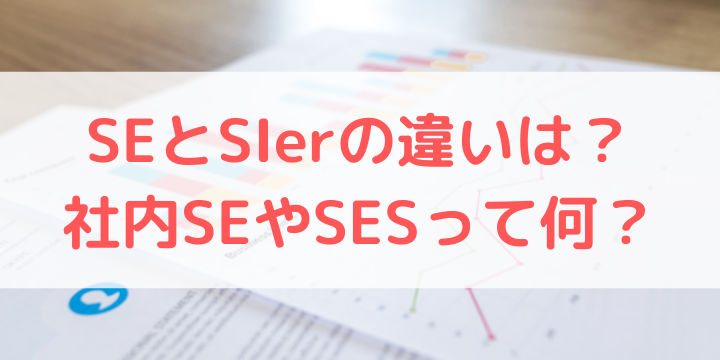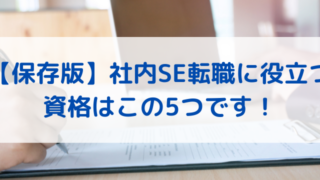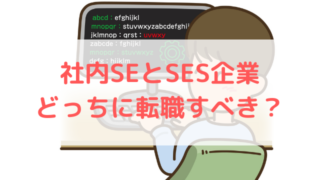こんにちは。まよ(@josysnohito)です。
IT業界への就職を志した頃に聞くようになる「SIer」「SE」などの単語。横文字の多いIT業界の説明を聞いていて混乱してしまう人もいますよね。
この記事ではそんな疑問をお持ちの方に向けて、SIerとSEの違いやIT業界への就職活動でよく使われる横文字の解説をします。
SIerとSEの違いは?

SI/SIerとは?
まず、SI(System Integration)とは、お客様の情報システムを構築するお仕事のことです。
お客様のシステム化の要件をヒヤリングし、プログラムが動作するサーバーや複数のソフトウェアを組み合わせ、実際にプログラムを構築しながら「お客様のシステム一式」を納品するまでの一連の作業のことを指します。
そして、SIer(System Integrator)とは、SIのお仕事を主要事業としている企業のことです。
SIerはビルなどの建築工事を主要事業とするゼネコン比較され、ITゼネコンなどと呼ばれることもあります。
ビルを建てるために、土地や建築資材を調達し、職人さんを雇い、施工管理を行う事業と、システムを構築するために、サーバーやソフトウェアを調達し、エンジニアを雇い、プロジェクト管理を行う事業とが似ているためです。
SEとは?

SE(SystemEngineer)とは、システム開発やシステムの保守(メンテナンスなど)のお仕事をするエンジニアのことです。略さずにシステムエンジニアと呼んだ方がイメージしやすいかもしれませんね。
SIerで働くエンジニアのこともSEと呼びますし、SIerにシステム開発を委託する一般企業のシステム部門で働くエンジニアのこともSEと呼びます。後者はSIerのSEと区別して社内SEと呼ばれます。
SEには大まかに分けると以下の2パターンの職種があります。
アプリケーションエンジニア(アプリ系SE)
情報システムは必ず、システムが動くインフラとなるサーバーやOSと、その上で起動するアプリケーションとで成り立っています。
例えば皆さんのスマホも「本体やOS(AndroidやiOS)」といったインフラの上で、「アプリ」を起動しますよね。
この、アプリケーションの部分の構築を担当するのがアプリ系のSEです。
インフラエンジニア(インフラ系SE)
一方、アプリケーションが動く、サーバーやOSなどの整備を行うのがインフラ系のSEです。
サーバを調達し、その上にOSをインストールし、外部システムとのネットワーク回線を敷設し、アプリ系のSEがシステム開発を行う基礎部分を構築します。
もちろん、インフラを構築するための要件定義や保守作業に携わることもあります。
インフラ系エンジニアはアプリ系エンジニアと比較し、なかなか個人で技術を習得するのが難しい(サーバやネットワークの設備の調達に多額の費用がかかる)ため、一定以上の技術を習得すると、非常に重宝される技術者になれます。
最近はAWS(AmazonWebServices)のようなクラウドサービス上にアプリケーションを構築する事例が増えていますが、これは自前でサーバを用意してOSをインストールするか、他社が構築した大規模なサーバの一部を間借りするかの違いです。
ちなみに・・・
企業によってアプリ系SEのことのみをシステムエンジニアと呼んだり、インフラ系SEをネットワークエンジニア、データベースエンジニアなどに分割したり、営業寄りのエンジニアのことをセールスエンジニアなどと呼ぶこともあります。
この呼び方は多種多様なので、SEは大まかに分けるとアプリ系とインフラ系の2種類に分かれると覚えておけばOKです。
SESとは?
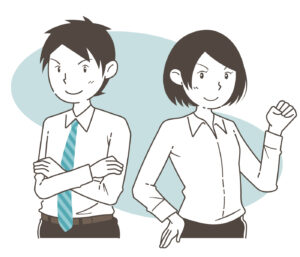
SES(System Engineering Service)とは、システム開発や保守作業を委託するサービスのことです。このサービスの契約をSES契約と呼びます。要はSEの派遣事業です。
建築工事において職人さんを集めるのと同様、システム開発の仕事でもSEを集める必要があり、この場合の契約形態の一つとして採用されています。
SES契約ではSEの労働力が商品となり、時間単価という基準が採用され、概ね1時間あたり3000円~6000円程度の単価での契約となります。SES契約を遂行するSEは客先のオフィスに常駐し、技術的なサービスを提供するお仕事に携わります。
派遣する側が自社サービスをひとつも持っていなくても、労働力の提供するだけで売上を上げられるのが何よりの魅力です。
人手さえあれば売上をあげられるので、SESのみを主要事業とする企業も存在しますし、自分自身のスキルを商品にSES契約を企業と結び生計を立てるフリーランスエンジニアも存在します。
しかし「SESはやめておけ」など、SES契約に対して悪い評判を聞いたことがある人も多いはず。
本来、「エンジニアが必要な企業」と「スキルを報酬に変えたいエンジニア」を結ぶための仕組みなのですが、経験の浅いエンジニアを一線級のエンジニアのように派遣する企業が少なからず存在するため、受発注者双方に負のイメージが残るためだと考えられます。
SIerのSEと社内SEの違いは?

ここからはこのような質問にお答えします!
SIerのSEと社内SEの違い
違い1:受注者か、発注者か
SIerは基本的にはシステム開発を請負う受注者の立場でお仕事をすることになります。そのためお客様が何をやりたいかをヒヤリングし、お客様のやりたいことをシステムで実現するのが主な業務内容です。
SIerのSEは自分が作りたいものではなく、お客様の要件をもとにシステム開発を行っていく必要があります。あくまでお客様ありきのお仕事です。
一方、社内SEはシステムを発注する立場で仕事をすることになります。そのため、社内SEはシステム開発の目的と費用対効果を考慮した上で、明確な要件をSIerに提示することが求められます。(これができないとSIerの担当者に「あの客は曖昧な要件しか出せない」と愚痴られる)
要件定義工程はSIerが支援してくれることも多いですが、SIerは開発量を増やせば増やすほど自社の売上が上がる立場であるため、必ずしも利害関係が一致する立場ではありません。言いなりにならず、自らの考えで要件を検討する必要があります。
違い2:システムを構築するか、ビジネスを構築するか
SIerはお客様のシステムを構築するのが主なお仕事です。お客様からシステムを開発・保守する費用をもらって、その金額内に人権費が収まるようにコントロールします。
そのため、SIerのSEはシステムを構築する技術力や、定められた期限までにプロジェクトを完遂させるマネジメント能力が求められます。
一方、社内SEはシステムを使って利益を生み出せるビジネスを構築するのがお仕事です。例えば銀行なら、ATMを使って手数料を稼いだり、人件費を削減したりしていますよね。
違い3:幅広い業界に関わるか、自社の業務に特化するか
SIerのSEは様々な業界のお客様の業務やシステムに携わって、幅広い経験を積むことができます。
システム開発に伴う幅広い知識や、複数のプロジェクト関係者を束ねるマネジメント能力が身につくため、一般的に転職市場において評価が高く、システムに絡む職種であれば幅広い業界に転職することのできる経験値を積むことができます。
一方、社内SEは自社の業務に特化した仕事を行います。特定の業界のお仕事に愛着がある場合、その分野の業務に腰を据えて取り組むことができます。
転職の際はSIerほど幅広い選択肢が用意されないものの、業界内での転職は非常に容易に行うことができたりします。
この、ITに絡む幅広い業務を経験することができるか、特定の業界に特化するかがSIerのSEと社内SEの大きな違いです。
まとめ:IT業界には多種多様なポジションが存在する

横文字を使う人が多いIT業界ですが、正しく理解できればたいして難しい事は言っていなかったりします(笑)
IT業界の用語を説明しながらSIerのSEと社内SEの違いをご紹介しましが、IT業界と一言で言っても、プログラムを組むお仕事だけじゃなくて多種多様な仕事があることをご理解いただけたかなと思います。(むしろプログラムを組まない仕事をする人のほうが多いくらいです)
小難しい言葉を正しく理解して、自分にあったポジションを見つけてみてください!